都知事選は、石原慎太郎の圧勝という結果。
結局、終わってみると、対立候補の主張もマスコミの風潮も、一般的な都民の感覚とずれていたのではないか、という気がしてならない。
たとえば自分が一番ずれていると思っていたのは、オリンピック誘致問題。「このご時世に五輪なんかにお金かけている余裕はない」と本気で思っていた都民は少ないだろう。個人的には、五輪をやるなら是非東京でやって欲しいと思っているし、石原さんが「お金には変えられない価値がある」というのはとても理解できる。五輪招致自体が石原さんの鶴の一声で始まったようなプロジェクトだけに、対立候補としては標的にしやすいというのはあったと思うが、そもそもこういう将来に希望が持てるような明るいプロジェクトを批判して議論するというのは、選挙の作戦としてははずれだったんじゃないかなぁ。
といって、今の東京に、選挙の争点となるような問題があるのか、と言われると思い浮かばないのもまた事実。豪遊問題とか四男問題とか細かい問題はいくつかあったし、石原さんのワンマンショーに対して嫌悪感を持っていた人もたくさんいたとは思うけど、総じて都民は石原都政に対し、一定の評価を下していたのだろう。逆に、この細かい問題をさも重大な問題のように連日取りざたしていたマスコミの方が、民意を読み違えたのかも知れないなぁ、と感じている。
自分も石原さんは都知事としてよくやっていると思うし、やっぱり「ものが言える人」がトップに立っていてくれると安心できるところがある。ただ、2期目は1期目と比べても随所にワンマンっぽいところが目立っただけに、3期目になってさらにこの傾向が強くならないといいのだが。
しかし、石原さんも74歳ですか、、、。あの元気さを見ていると、とてもそんな歳には見えないよなぁ。任期満了する頃には78歳ということで、かなりの高齢にはなるけど、途中で倒れないように、元気で頑張って欲しいです。
アル・ゴア「不都合な真実」
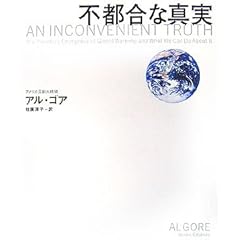
元アメリカ副大統領のゴアさんが、自身のライフワークとも言うべき地球温暖化問題に対してまとめた本。
自分も地球温暖化をはじめとする環境問題については大いに関心があるし、何とかしなければという思いも強く、ちょっと前に購入してあったんだけど、なかなか読む暇がなく、今日やっと読んでみた。
いやー、この本はすごいです。元々ゴアさんがいろんなところで演説に使ってたスライドをベースとしているということもあるけど、何より写真や図表がふんだんに使われているのでとてもわかりやすい。
今地球が直面している地球温暖化の問題が、一刻の猶予も許されない事態であるということ、今既に悲惨な状況に陥っている地域があるということ、そして今後50年の間にどんなことが起こりえるのかがとてもよく分かった。
温暖化がちょっとでも気になる人は、ぜひこの本を読んでみて欲しい。
# たぶん、ブッシュと Exxon Mobil が嫌いになると思うけど。。。
今年の暖冬が温暖化の一環だという主張もある一方で、じゃあ温暖化を防ぐためにみんなが努力しているかというと、これは全然なってないだろうと思う。暖冬とはいっても寒いことは寒いし、傾向的な温暖化をなかなか実感できない訳で、その意味で他人事だと思っている部分もあるのだろうけど、それよりも何よりも、今の便利な生活を犠牲にしてまで温暖化を防ぐ意味があるか、というある意味刹那的な考えを持っている人が多いこと、それに自分一人が何かしたところで全体的な温暖化は止められないと思っている人が多いことが原因なんじゃないだろうかと、個人的には思っている。
確かに自分の生活を犠牲にするのは難しいことだけど、でも、自分にできることをちょっとずつでも実践することが、「塵も積もれば山」で大きく効いてくると思っているし、実際この本にはそれを示すデータもいくつか載っている。
とりあえず、
- 電球を省エネなものに変える
- 極力飛行機を避け、可能なら電車を利用する
- クーラーの設定温度を1〜2℃上げる
とか、その辺は実践していかないとね。
- 2007.02.25 Sunday
- 社会
- 22:38
- comments(4)
- -
- by taishi
違和感
このところ世間を騒がしている2つの事件。どちらも市民をだましていたという点については非難されてしかるべきだとは思うが、事態の過熱ぶりに違和感を感じているのは自分だけだろうか。
ここのところの報道を見ていると、さも人命に関わるような重篤な事態を引き起こしたかのような仕打ちを受けている。違反は違反として処罰の対象となるのは仕方ないにしても、他の重大な刑事事件と比べても騒ぎすぎな気がしてならない。
話はそれるが、これら2つの事件に関しては、事件の本筋とは関係のないところで「何だかなぁ」と思うことがある。(というか、これが今日の本論。)
まず不二家の件。消費期限が切れた食材を使わないというルールは安全を考えた場合には非常に合理的だけれど、たとえばたった1日過ぎたぐらいで「食べ物」を廃棄していいのだろうか。特にチョコレートのように、衛生的にそれほど危険でないイメージがあるものを無駄に捨ててしまっているのを想像すると、とてももったいなく感じる。もちろんこれは仕入れの段階での見通しが甘いからこうなるのだろうけど、何にせよ食べ物を粗末にするのはとてもいやな感じがする。何とか廃棄以外の方法を見いだせないものだろうか。
次にあるあるの件。そもそも視聴者がテレビに影響されすぎ。勝手に乗せられといて、ちょっと根拠がぶれた途端に「嘘つき」扱いするのはどうなんだろうか、、、。情報というのは、あくまで受け取った側で取捨選択して初めて有効な情報となり得るわけで、テレビで言っているからと何も考えずに鵜呑みにしてはいけないということに視聴者も気づくべきだと思う。(特にこういう番組だからこそ。)
ところで、違和感といえば、東国原英夫知事。この呼び名も相当違和感がある。。。今日は登庁初日でいきなり鳥インフルエンザの問題が再発したりして、まさに前途多難ではあると思うけど、何にせよ頑張ってほしいなぁと思う。
ここのところの報道を見ていると、さも人命に関わるような重篤な事態を引き起こしたかのような仕打ちを受けている。違反は違反として処罰の対象となるのは仕方ないにしても、他の重大な刑事事件と比べても騒ぎすぎな気がしてならない。
話はそれるが、これら2つの事件に関しては、事件の本筋とは関係のないところで「何だかなぁ」と思うことがある。(というか、これが今日の本論。)
まず不二家の件。消費期限が切れた食材を使わないというルールは安全を考えた場合には非常に合理的だけれど、たとえばたった1日過ぎたぐらいで「食べ物」を廃棄していいのだろうか。特にチョコレートのように、衛生的にそれほど危険でないイメージがあるものを無駄に捨ててしまっているのを想像すると、とてももったいなく感じる。もちろんこれは仕入れの段階での見通しが甘いからこうなるのだろうけど、何にせよ食べ物を粗末にするのはとてもいやな感じがする。何とか廃棄以外の方法を見いだせないものだろうか。
次にあるあるの件。そもそも視聴者がテレビに影響されすぎ。勝手に乗せられといて、ちょっと根拠がぶれた途端に「嘘つき」扱いするのはどうなんだろうか、、、。情報というのは、あくまで受け取った側で取捨選択して初めて有効な情報となり得るわけで、テレビで言っているからと何も考えずに鵜呑みにしてはいけないということに視聴者も気づくべきだと思う。(特にこういう番組だからこそ。)
ところで、違和感といえば、東国原英夫知事。この呼び名も相当違和感がある。。。今日は登庁初日でいきなり鳥インフルエンザの問題が再発したりして、まさに前途多難ではあると思うけど、何にせよ頑張ってほしいなぁと思う。
- 2007.01.24 Wednesday
- 社会
- 00:16
- comments(3)
- -
- by taishi
未履修
例の未履修問題。
日本の教育に関する様々な問題が、この一件で浮き彫りになったような気がする。
今回の件は、大学受験で少しでも有利になるようにとの高校側の配慮なんだろうけど、そもそも大学受験ってそんなに大事なことなんだろうか。
いい大学に行けば、いい会社に入れていい生活を送れるというのは、ステレオタイプとしては間違っていないんだろうけど、何か根本的なところで重大な誤りを犯している気がしてならない。
そもそも社会人としては「どこの大学を出たか」じゃなくて「どれだけ仕事ができるのか」の方が遙かに重要なはずで、いくら勉強ができても基礎の部分の構築が疎かな人間が仕事をこなせるようになるとはとても思わない。誤解を恐れずに言えば、学歴が高いけど仕事は微妙という人もいれば、逆に学歴がなくても人の何十倍も価値のある仕事をする人だっている。そうしたスキルは、もちろんただ勉強をこなすだけで身に付くものでもないし、幅広い知識や幅広い経験によって成り立つものだろう、と個人的には思っている。受験にしか役立たない知識を詰め込んで何となくいい大学に行ったところで、その後の人生で大きな壁が立ちはだかることになるだろう。
大学側にも大きな落ち度があるだろう。そもそも平成6年の学習指導要領改訂によって授業数が少なくなり、カバーできる範囲が狭くなったことは明らかなのに、肝心の入試がこの改訂についていけていないせいで、学校側も無理をしなければならなかったということがこの問題の背景があるようだ。確かに一度作られた評価基準を変えると言うことは「評価のブレ」にもつながるわけで、大学としても変更による大きなリスクをあまりとりたくないというのも分かるし、少子化に伴って優秀な生徒を集めないとというプレッシャーもよく分かるのだが、これも結局「自分の大学だけ良ければ」というエゴに過ぎない。
それと、その「人格」の形成をすべき「学校」という組織において、みずからが「ずるをしてでも人より前に出ろ」という姿勢を生徒に示すというのはあまりにもひどい。高校というのは専門教育の機関でもないだろうし、むしろ人間としてしていいこと、してはいけないことを教えるのが本来の姿なはず。先生が「ばれなきゃ何しても大丈夫」みたいな考えであれば生徒も同じように育つのは自明だし、受験戦争の弊害による「自己主義的」価値観と相まって、「よくない大人」が大量生産されていないことを祈るばかり。
ま、この問題については生徒には (ほとんど) 非がないわけで、不正をしてきた学校、チェックを怠ってきた文部科学省は攻められても仕方ないと思う。ただ、受験のことしか頭にない保護者も、広い意味でこの事件の加害者な訳で、本当に子供のことを考えるなら、受験以外のことにも気を配る配慮をして欲しいと思う。
受験だけが人生じゃないよ、ということかな。
日本の教育に関する様々な問題が、この一件で浮き彫りになったような気がする。
今回の件は、大学受験で少しでも有利になるようにとの高校側の配慮なんだろうけど、そもそも大学受験ってそんなに大事なことなんだろうか。
いい大学に行けば、いい会社に入れていい生活を送れるというのは、ステレオタイプとしては間違っていないんだろうけど、何か根本的なところで重大な誤りを犯している気がしてならない。
そもそも社会人としては「どこの大学を出たか」じゃなくて「どれだけ仕事ができるのか」の方が遙かに重要なはずで、いくら勉強ができても基礎の部分の構築が疎かな人間が仕事をこなせるようになるとはとても思わない。誤解を恐れずに言えば、学歴が高いけど仕事は微妙という人もいれば、逆に学歴がなくても人の何十倍も価値のある仕事をする人だっている。そうしたスキルは、もちろんただ勉強をこなすだけで身に付くものでもないし、幅広い知識や幅広い経験によって成り立つものだろう、と個人的には思っている。受験にしか役立たない知識を詰め込んで何となくいい大学に行ったところで、その後の人生で大きな壁が立ちはだかることになるだろう。
大学側にも大きな落ち度があるだろう。そもそも平成6年の学習指導要領改訂によって授業数が少なくなり、カバーできる範囲が狭くなったことは明らかなのに、肝心の入試がこの改訂についていけていないせいで、学校側も無理をしなければならなかったということがこの問題の背景があるようだ。確かに一度作られた評価基準を変えると言うことは「評価のブレ」にもつながるわけで、大学としても変更による大きなリスクをあまりとりたくないというのも分かるし、少子化に伴って優秀な生徒を集めないとというプレッシャーもよく分かるのだが、これも結局「自分の大学だけ良ければ」というエゴに過ぎない。
それと、その「人格」の形成をすべき「学校」という組織において、みずからが「ずるをしてでも人より前に出ろ」という姿勢を生徒に示すというのはあまりにもひどい。高校というのは専門教育の機関でもないだろうし、むしろ人間としてしていいこと、してはいけないことを教えるのが本来の姿なはず。先生が「ばれなきゃ何しても大丈夫」みたいな考えであれば生徒も同じように育つのは自明だし、受験戦争の弊害による「自己主義的」価値観と相まって、「よくない大人」が大量生産されていないことを祈るばかり。
ま、この問題については生徒には (ほとんど) 非がないわけで、不正をしてきた学校、チェックを怠ってきた文部科学省は攻められても仕方ないと思う。ただ、受験のことしか頭にない保護者も、広い意味でこの事件の加害者な訳で、本当に子供のことを考えるなら、受験以外のことにも気を配る配慮をして欲しいと思う。
受験だけが人生じゃないよ、ということかな。
- 2006.11.04 Saturday
- 社会
- 00:14
- comments(3)
- -
- by taishi
5回目の September 11th
あのおぞましい事件から早くも5年。
ちょうど5年前、会社から帰ってつけていた TV に映し出された映像を目にした際の衝撃は今でも忘れることが出来ない。2機目が突っ込んだ瞬間。タワーが崩壊する瞬間。目の前で起こっていることが信じられなかったし、どうしてこんなことが起こったんだろうと呆然と TV の前に座り込んでいたという記憶が残っている。
あれから5年。この事件を機にアメリカはテロ掃討へと猛進し、アフガンを攻め、イラクのフセイン政権を崩壊させた。しかし、テロへの恐怖は衰える気配もないし、「負の連鎖」から互いに憎しみあい、同じ人間同士を傷つけ合う戦争が世界の至るところで行われている。
あの時アメリカが取った方針は、国家を守るという意味では間違っていなかったとは思うが、暴力に暴力で応酬するという愚挙では何も解決しないと言うことが浮き彫りになっただけのような気もする。
先日、高校の同級生が、レバノンにいる友人からのメールをブログに載せていた。当時レバノンは武装組織ヒズボラによる兵士誘拐事件に怒ったイスラエルに侵攻されていて、ヒズボラとは全く無関係の民間人が空爆により多数無くなったというのはご存じの通り。その友人からのメールでは、彼女の友人、知人が毎日たくさん犠牲になっていくという悲惨な状況が切実に訴えられており、こうした生の声を目にすると、どうしてこんなことになってしまうのか、もっと他に解決の方法はなかったのか、ヒズボラもイスラエルも互いに歩み寄ることは出来なかったのかと、何ともやりきれない気持ちになる。我々はこうした悲惨な状況も TV のニュースでせいぜい1日に数十秒程度目にするだけだが、平和な日本にいるからこそ、世界ではいつもどこかでこうした悲惨な行為が繰り返されていると言うことを忘れてはならないと思うし、せめて日本だけは、どんなに時代が流れても、暴力に対して報復的軍事措置を取るような国になって欲しくないと思う。もちろん国が侵攻された際にこんな甘く悠長なことを言っていられる訳がないという意見もあると思うが、暴力を封じるための暴力は、結局さらなる暴力を生み出すだけであり、最後に残るのは「無」でしかないということは理解して欲しいと思う。
ちょうど5年前、会社から帰ってつけていた TV に映し出された映像を目にした際の衝撃は今でも忘れることが出来ない。2機目が突っ込んだ瞬間。タワーが崩壊する瞬間。目の前で起こっていることが信じられなかったし、どうしてこんなことが起こったんだろうと呆然と TV の前に座り込んでいたという記憶が残っている。
あれから5年。この事件を機にアメリカはテロ掃討へと猛進し、アフガンを攻め、イラクのフセイン政権を崩壊させた。しかし、テロへの恐怖は衰える気配もないし、「負の連鎖」から互いに憎しみあい、同じ人間同士を傷つけ合う戦争が世界の至るところで行われている。
あの時アメリカが取った方針は、国家を守るという意味では間違っていなかったとは思うが、暴力に暴力で応酬するという愚挙では何も解決しないと言うことが浮き彫りになっただけのような気もする。
先日、高校の同級生が、レバノンにいる友人からのメールをブログに載せていた。当時レバノンは武装組織ヒズボラによる兵士誘拐事件に怒ったイスラエルに侵攻されていて、ヒズボラとは全く無関係の民間人が空爆により多数無くなったというのはご存じの通り。その友人からのメールでは、彼女の友人、知人が毎日たくさん犠牲になっていくという悲惨な状況が切実に訴えられており、こうした生の声を目にすると、どうしてこんなことになってしまうのか、もっと他に解決の方法はなかったのか、ヒズボラもイスラエルも互いに歩み寄ることは出来なかったのかと、何ともやりきれない気持ちになる。我々はこうした悲惨な状況も TV のニュースでせいぜい1日に数十秒程度目にするだけだが、平和な日本にいるからこそ、世界ではいつもどこかでこうした悲惨な行為が繰り返されていると言うことを忘れてはならないと思うし、せめて日本だけは、どんなに時代が流れても、暴力に対して報復的軍事措置を取るような国になって欲しくないと思う。もちろん国が侵攻された際にこんな甘く悠長なことを言っていられる訳がないという意見もあると思うが、暴力を封じるための暴力は、結局さらなる暴力を生み出すだけであり、最後に残るのは「無」でしかないということは理解して欲しいと思う。
- 2006.09.11 Monday
- 社会
- 22:33
- comments(0)
- -
- by taishi
- 表示しているエントリー
-
- 東京都知事選 (04/09)
- アル・ゴア「不都合な真実」 (02/25)
- 違和感 (01/24)
- 未履修 (11/04)
- 5回目の September 11th (09/11)
- コメントリスト
-
- 人身事故で運転見合わせ
⇒ taishi (03/02) - 人身事故で運転見合わせ
⇒ たろう (03/02) - 遅ればせながら、今年の抱負
⇒ よーこ (01/17) - 有馬記念、そして東京大賞典
⇒ minom (12/30) - オフィス閉鎖
⇒ sana (11/28) - 練習 2009/11/11
⇒ minom (11/16) - 練習 2009/11/11
⇒ taishi (11/12) - 練習 2009/11/11
⇒ minom (11/12) - 天皇賞(秋)・予想
⇒ minom (11/01) - 秋華賞
⇒ taishi (10/19)
- 人身事故で運転見合わせ