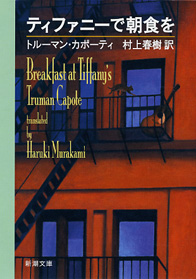上司に読めと薦められて読んだ本。
影響力とは、自分のして欲しいことを相手にしてもらうために発揮すべき力のこと。一般的に仕事について言うと、上司と部下のような権力差のある関係では上から下へものを頼むのは頼みやすいが、現実には部門横断的に仕事を頼まないとならないケースや、部下から上司へお願い事をするケースも多々ある。そういう場合にどういうやり方で頼めば相手は動いてくれるか、という点についてノウハウをまとめた本。
影響力の基本は、なんと言っても Give and Take の考え方である。つまり、相手が欲しいものをこちらから提示して上げることによって、自分の欲しいものを引き出すというのがベースにあるということ。一見すると相手が欲しがっているものを自分がいつもいつも持っているわけではないとも思えてしまうが、多くの場合「相手はこれが欲しいに違いない」という際には考える側の主観が入るわけで、必ずしも相手の立場に立って考えていないことも多いと著者は主張している。ちょっと見方を変えれば実は相手の欲しいものが意外と提供できるかも知れないし、その「見方の変え方」みたいなもののテクニックが数多く収録されている。
「常日頃から相手と良い関係を築いておきなさい」とか、非常に日本的とも思える主張が随所に出てくるのにはちょっと驚いた。アメリカでもこういうやり方が必要となるんだというのは新しい発見だった。
仕事をしていると、「あの部署が動いてくれないから…」とか「この人がもっとこうしてくれたらいいのに」と思うことは非常に多いが、そうした場合にでも自分の努力次第で何とかなるというのはある意味勇気をもらったような気がする。今後仕事を進めていく上でも参考にしたいと思う。(とはいえ実践するのはなかなか難しいが。。。)