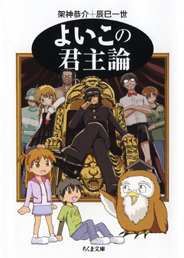久々の書評。
博報堂でディレクターを務める須田さんが、これからの時代にあった広告の手法として提唱する「使ってもらえる広告」というコンセプトについて、自身の経歴やこのコンセプトに至る過程なども含めて解説した本。
「使ってもらえる広告」というキャッチコピー自体はとてもいいと思う。ただ、書いていることはどれも客相手の商売であれば当たり前のことを焼き直しただけに過ぎず、逆に広告業界 (とくにマスメディアを用いた広告) がいかにユーザを見ていないかを露呈しているかのような逆効果もあって、正直がっかり。
個人的な考えでは、広告とは「広告の掲載主の利益を生むために、対象となる人々に意図した行動を取らせようとするあらゆる活動」を差すものだとと理解している。その意味で、たとえば「ミクシィ年賀状」なんかはユーザに年賀状を出すという行為を促進させる効果があったわけで、ツールとして価値があったという評価は正しい。ただ、ミクシィ年賀状というツールそのものを広告と呼んでいいのかという点は、この本を読んでもさっぱり分からなかった。書では例として、ミクシィ年賀状の効果は年賀状発行枚数の増加に現れた、だからこれは広告の一形態だ、というような主張をされているが、これが広告というのであれば、広告を依頼する主体はあくまで日本郵政であるべきで、それがこの本には一切書かれていない。何となくミクシィとかその辺の団体が「こういう仕組みを作ってマージンとれれば儲かるんじゃない?」というような発想で始めたサービスであるだけで、そこに日本郵政の積極的な参画があったようには読めなかった。だとすれば、ミクシィ年賀状には広告としての効果はなかったんじゃないか、参画していない第三者に利益を与えることが広告といえるのかという点については疑問が残る。
あまり予断を下してはいけないんだろうけど、何となく、いままでテレビの世界にいてネット上での動きに詳しくなかった人が、いきなりネットを扱うことになって、次々と目にする新しいものに飛びついてはしゃいでいるだけのようにも見えてしまった。
正直あまり得るものはなかったかな。残念ながら。