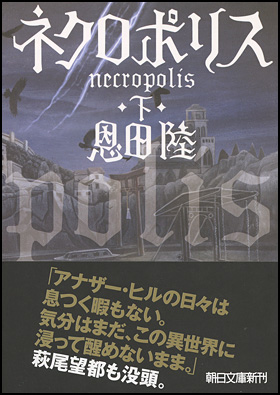絲山秋子を読むのはこれで3作目。
この本は芥川受賞作でもあるが、表題の「沖で待つ」をはじめとした全く毛色の違う短編が3つ収録されている。
最初の「勤労感謝の日」は、やむを得ない事情により会社を辞めざるを得なくなった30代後半の女性の、卑屈ではあるが何ともやるせない日常を綴った作品。ちょうどバブルの頃は女性総合職という言葉が世間をにぎわせていたように思うが、正直まだまだ社会が働く女性の扱いにとまどっているような時代でもあり、そんな中でがむしゃらに働けどもまともに扱われないことで苦労した女性もさぞかし多いことだろう。嫌なことが続くと人間誰しも思考がネガティブな方向に進んでしまうし、プラス思考しろと言われても土台無理な状況があるというのは間違いない。しかしそれをよりどうしようもなく描写したり、そんな中でもちょっとした自分の居場所を見つけたりする様子を描くことで、こうした状況に置かれている女性に対してエールを送っているのではないかと思った。
2つ目の「沖で待つ」もやはり総合職として会社に入った女性が主人公。同期と2人で福岡配属になり、見知らぬ土地で最初は苦労するものの徐々にそんな状況にも慣れという状況の中で、男女の差はあれども同期としての固い絆を築いていくという友情の物語。心から信頼し会える友人がいるというのは非常に心強いことだろうけど、そんな友人を見つけるというのはまた非常に難しいこと。男女の違いはあるが、同期という同じ時代に同じ不安を抱えて仕事に従事した経験はやはり信頼関係の構築に大きく寄与すると思うし、その意味では自分も同期を大事にしなければ行けないなぁ、と考えさせられた。
最後の「みなみのしまのぶんたろう」はちょっと変わった作品。何せこの作品、漢字が1文字も使われていない。主人公は大臣の座から失脚した「しいはらぶんたろう」。都会で権力を操り、わがままが通って当然という環境に慣れきっていたぶんたろうが、南の島に左遷させられて少しずつ考え方を変えていったり視野が広くなっていく様子を、絵本チックな語り口で描写している。最終的に何が言いたかったのか正直よく分からない作品ではあるが、ぶんたろうが徐々にピュアになっていく姿というのは何というか滑稽でおもしろい。
この本も前回同様とても面白かった。また次の作品が出たら是非読んでみたい。