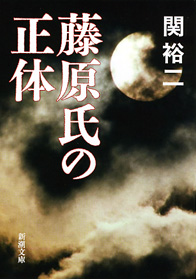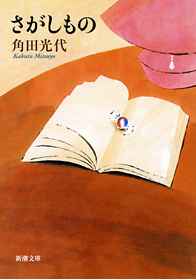うちに何故か東野圭吾の未読の本が大量にあるので、これからしばらくは東野圭吾強化月間とすることにした。
で、まずはこの作品。
先天性の病気を持ち早世した時生。死ぬ瞬間に20年以上前にタイムスリップして当時23歳だった父親の拓実と出会うが、当時の拓実は全くのダメ男。ついに愛想を尽かして逃げられてしまった彼女。千鶴を追って2人で大阪へ向かうが、千鶴の抱えるトラブルに拓実と時生も巻き込まれてしまう。そのトラブルを解決していく過程の中でやがて拓実が人生にとって大事なものを見つけて更正していく、といったストーリー。
東野圭吾らしくないというか、非常に感動的なストーリー。特に最後に拓実が名古屋に立ち寄るシーンは涙なくしては語れない。緻密なトリックとかは全然出てこないが、それでも東野圭吾らしい伏線が随所に散りばめられていて読んでいて飽きることがない。500ページ強もあるちょっと重めの本だったけど、実質3日ぐらいで読破することができた。
街の様子とか、名古屋や大阪での再開のシーンとか、相変わらず細かい描写がうまいので、光景が目に浮かんでくるようだった。お涙頂戴的な要素もあるので、ドラマにしたら視聴率取れそうな感じ。
1発目からなかなか幸先のいいスタート。続きの本も面白いといいなぁ。