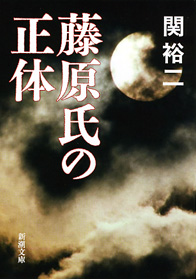
「藤原氏」とは、日本人ならみなが知っている平安時代に活躍した貴族の家系。藤原道長・頼通に代表される摂関政治が有名であるが、奈良・平安を通じて時代の中心だった藤原氏について研究し、そのルーツについての仮説を立てたノンフィクション。
藤原氏の始祖と言えば何と言っても藤原 (中臣) 鎌足。中大兄皇子と起こした乙巳の変により大化の改新を成し遂げたことで有名だが、実は中臣鎌足自身の出自については分からないことが多いらしい。そこで氏は実は中臣鎌足は当時の百済の王で白村江の戦い以降行方が分からなくなった豊璋であったという説を展開している。そして、豪族の出ではないという出自を巧妙に隠蔽するために息子・藤原不比等が書かせたのが日本書紀であるとしている。こうした論調が現代の考古学上でどれだけ認められているのかは分からないが、少なくとも関氏が挙げている根拠にはいちいち納得できるものがあるし、非常に斬新なアイディアだと思う。
また、本の後半ではその後藤原氏が数々の政争に打ち勝って頂点に上り詰めるまでの過程について考察している。特に藤原氏は他の貴族らとうまくやっていこうとする気はさらさらなく、とにかく自分たちの家系に富と権力を集中させ、対抗勢力を策謀によってけ落としながら繁栄してきたとして、その姿勢を糾弾している。確かにこうしたやり口はほめられたものではないが、この時代は甘いことを言っていては乗り切れる時代ではなかっただろうと思うし、食うか食われるかという状況を乗り切るにはやむを得なかった部分もあるのではないだろうかと思う。菅原道真に代表される藤原氏に追い落とされた被害者にしても、結局は政治的な駆け引きに強くなかったと言うことなんだろうし。それと、こうした1000年も前の藤原氏の姿勢を持ち出して現代にも適用しようとする氏の主張は、正直行き過ぎな気もした。
とはいえ、藤原氏を中心に描くことで奈良・平安前中期の史実をわかりやすくまとまっているので、時代背景を理解するのには大変役立った。この時代については普段あまり時代劇なんかでも演じられることがないので知識が乏しかったが、さすがにいろいろあったんだなぁ、と大変勉強になった。
余談だが、ここに歴史ノンフィクションもののレビューを書くのはもしかしたら初めてかも知れない。が、小さい頃は考古学者になりたかったぐらいで歴史物には非常に興味がある。歴史的な記述を目にして古代に思いを馳せるという考古学の醍醐味を改めて味わった気がする。またいい本があれば読みたいと思う。
# しかしこの本は読破に時間がかかった。。。