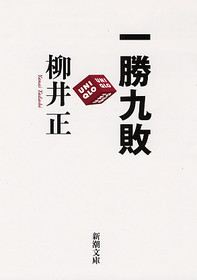著者のクルーグマンは国際経済学者で、ともすると国際的競争力を保つために保護主義に走りそうになっていた90年代前半のアメリカの政治において、確固たる経済理論を用いてその危険さを説き、そうした活動が認められて2008年にノーベル経済学賞も受賞している。この本はその当時に発表された氏の文書や講演を1つの本にまとめたものであり、1998年に出版されたものが昨年文庫で再発売されたものとなっている。
クルーグマンの主張は首尾一貫している。当時アメリカではびこっていた考え方は、アジア各国をはじめとする発展途上国へ資本が移動し、それに伴って特に製造業の雇用が深刻な打撃を受けているとした上で、国内の雇用を守るためには途上国からの輸入に制限をかけて自国を保護すべきであるという考え方である。が、この考え方のよりどころとして当時もてはやされていたバックグラウンドは、クルーグマンに言わせれば経済学の初歩の理論を使うだけでただちに間違いだとわかるような代物であるし、また輸入超過が国民の生活水準に与える影響は、国内総生産との比率を考えてみてもきわめて限定的であるので、大騒ぎするようなものではないとしている。
特に、1950年代に驚異的な経済成長を見せた東欧諸国と、1990年代にやはり急激な成長を遂げたアジアの状況を比較し、構造的には実はほとんど同じであるとした論調には、アジアの成長が止まってきている2009年に改めて振り返ってみても当たっていると思うし、当時の潮流に抗ってこうした主張を繰り広げていたクルーグマンはすごいと思う。
よくよく考えてみると、収入とは経済活動を通して得られる付加価値に対する対価であり、この構造は今も昔も変わらない。付加価値とはすなわち自分にはできない何かを他者が成し遂げてくれることに対する対価であり、その意味で貿易はお互いに足りないものを補う意味で双方にとって利益を生む行為である。その貿易を国策によって制限するということは、すなわち付加価値を提供する相手が限定されることに他ならない。その意味で、保護主義的政策が国内の不況への対策にはならないだろうというのは直感的にもわかりやすい。
しかし経済学についてほとんど知識のない自分が読むにはかなりつらい本だった。。。クルーグマンも言っているとおり、経済について語るのであれば最低限基礎の経済学ぐらいは理解していないと、思わぬ方向にいってしまうということなんだろう。正直今の自分が読むにはあまりにレベルが高くて、クルーグマンの説いている主張の本質までは全く理解できていないだろうと思われる。やっぱりちゃんと勉強しないとだめだな。。。
最近経済学には非常に興味が出てきているだけに、今度はもうちょっと基本的なところから理解できるような本にトライしてみたい。