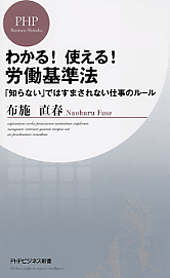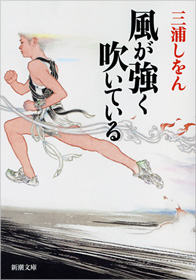タイトル通り、裁判員制度に必ずしも賛成でない立場を取る筆者が、裁判に対する歴史や考え方の変遷をふまえて、なぜ裁判員制度が導入されるに至ったかという点や、筆者が裁判員制度に賛成しない理由についてを記した本。
裁判員制度の是否について考えるには、そもそも裁判とは何で、どうして裁判制度が必要なのかをきちんと理解する必要がある。現代日本の刑事事件の裁判という制度が犯罪の抑止効果や犯罪者の更正を目的として実施されているというのは、漠然とは分かっていたものの、きちんと整理して解説してくれていてとてもためになった。刑事裁判は、被害者やその遺族の怨念を晴らすためにあるわけではないという点は、ともすると「被害者感情」の議論に終始しがちな最近のマスコミの報道姿勢ばかりを見ていると見失いがちで、誤解のないように常に気をつける必要があると感じた。
以前のエントリーでも書いたように、日本人の裁判に対する関心や参加意識を向上するためにまず制度から変えていこうというやり方が本末転倒であるというのは、筆者とも相通じるところがあったし、裁判員制度について自分が疑問に感じていることに答えてくれていて非常にためになった。
総じて筋は通っていたように思うが、いまの裁判員制度に反対するあまり、最後の方では言いがかりっぽく聞こえる主張を多くされていたのは残念 (「推定無罪」の話をしておきながら自身が完璧な論証を出来ていないのを見るのは何とも歯がゆい)。
法学部とかで裁判制度とか法律について勉強した人から見れば初歩過ぎて面白くないとは思うが、自分のようなど素人には大変良い本だと思う。裁判員制度についてちょっと考えてみたいという人にはお勧め。