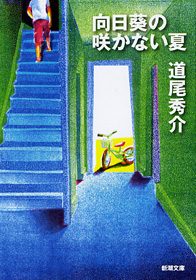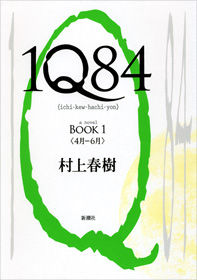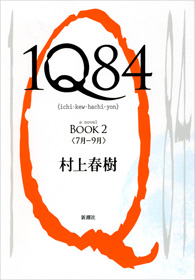ニンテンドーDS や Wii のヒットについて今更解説する必要もないだろうが、とにかくゲーム業界においては任天堂のひとり勝ち状態が続いている。なぜ任天堂はここまで売れる商品が作れるようになったのか、中興の祖である山内溥氏、跡を継いだ岩田現社長、そしてゲーム作りの天才とも言うべき宮本氏のキーパーソンの功績や考え方を紹介するとともに、任天堂が任天堂たるゆえんについて解説した本。
任天堂のすごいところは、娯楽産業の本質を正しく理解していると言うところにつきるだろう。娯楽というのは必ずしも日常に必要不可欠なものではないので、ちょっとしたことでユーザがすぐそっぽを向いてしまう。そうならないように細かいところに気を遣うとともに、ユーザに飽きられないように常に新しい試みを取り入れるというのは、他の企業が真似しようとしてもなかなか出来ないことだろう。
任天堂といえば、ソニーやマイクロソフトが高機能マシンに走った際に、我関せずという感じでどちらかというとローテクに終始したにもかかわらず、結果的に圧勝を納めた姿が何とも印象的だ。しかしそんな成功の裏には、ニンテンドー64やゲームキューブにおける大失敗があり、そこで学んだことを生かせたからこそ現在の隆盛があるわけで、決して一朝一夕で成し遂げられたものではないというのがよく分かる。
事実の羅列になっているのであまり読み応えはないけど、任天堂という会社の歴史としてみるといろいろと興味深い転もあって、勉強になった。