 |
|
 |
|
 |
| ガーナでビジネスをするレバノン人社長 |
 |
 |
|
| 都心の”ステーキハウス”で | ビジネスの話は一休み | |
 |
 |
|
| 社長のパートナー経営者 厳しい表情のイギリス人 |
柔和な目の奥は、鋭い |
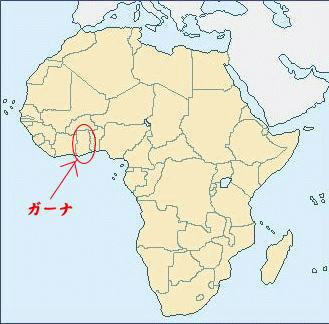 |
ガーナは、西アフリカのギニヤ湾の中央部に位置する。イギリスに長く植民され、植民地時代は、Gold Coast(黄金海岸)と呼ばれた。 第2次大戦後、1957年にブラック・アフリカ植民地の先頭を切って独立したが、その際、かつて西アフリカに栄えたガーナ王国(現在のマリのあたり)の名をとって国名とした。 (詳しくは、西アフリカのガーナ編でお伝えします) |
| 日本との関わりで顕著なものは、2つある。 一つに”野口英世博士” 熱帯地方で猛威をふるう、恐ろしい伝染病である「黄熱病」の研究のため、福島県出身で、アメリカに渡り、医学を修めた野口英世博士はガーナに渡り、偉大な研究成果をあげたが、惜しくも、現地で、自らも黄熱病にかかり、ガーナで没した。 博士の偉業を偲んで、現在、ガーナの首都アクラにあるガーナ大学の構内に、博士の”胸像”がある。 もう一つは日本への”カカオ豆”の輸出。 カカオ豆は、日本へ輸入された後、「ココア」やガーナの名を付けた「チョコレート」になっている。 |
|
| ガーナでビネスをする紳士二人が来日した。 一人は「レバノン人」。 もう一人は、「イギリス人」。 ガーナは、フランスの植民地が多かった西アフリカでは、数少ないイギリスの植民地であった関係で、今でもイギリスの影響が大きく、イギリス人が関係することが多い。 ブラックアフリカでは、レバノン人や、パレスチナ人ビジネスマンはさほど多くはないが、いずれも、白刃の修羅場をかいくぐってきた、強者たちで、一筋縄ではない。 眼光鋭く、顔は笑っていても、目の奥は笑っていない。 ステーキハウスで一時を過ごしたが、戦場のレバノンから、また、かつての植民地で仕事をするビジネスマンは、ひと味も、ふた味も違っている。 日本人も、国を失うくらいの”危機感”があれば、 逞しくなるのだろうか・・・ |
| 次話へ |