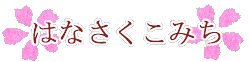

|
|
|
| ただただゆるりと歩を進める。この土地の他の木よりも少しだけ遅い桜は、薄紅の溶けない雪を風に舞わせ続けていた。物も言わずに連れ出した、その導きに、問い掛け一つ発せずに無言のままに着いてくるその姿を振り返る。 その薄紅と、深紅のコントラストに目眩いさえ覚えて。薄ら白い、その花の間に濃い緋紅の花が咲くような、その光景。 「紅緋衣だな…。」 ぽつ、と口を突いて出た言葉に、彼は小首を傾げる。いつもならば、よく通る低い声が問い掛けてくるが、今日はこの光景に気圧されでもしたのか、口を開かない。 「とても濃い紅色を持つ、桜の事だ。北方で咲くもので、俺も…数えるほどしか見た事がない。」 応える声に、あぁ、と小さく呟いて、自分の髪を指に絡め、静かに笑う。 花のように美しいものではないけれども、そう言うのなら、そう思っておこうか。今日はこの花の舞い散る中、少しは日頃の喧騒から遠ざかってもいい。そう思う。 少しだけ小高い丘の上。見通せる先の先まで続く、花の波。どこまでも続くその薄紅に宛ら花の上にでも立っているような幻を見る。懐かしいような、寂しいような、不思議な感覚。 手にしていた、小さな鞄の中から、朱の漆器の杯と鮮やかな青の小瓶を取り出して、桜に視線を彷徨わせていたヒトの目前に差し出してやる。漆器の底は、黒く塗られ、美しく図案化された桜が蒔絵で描かれて。途轍もなく使う季節を選ぶ代物だが、いつまでも自分の手元にありそうに思えてつい手に取ったのはほんの数日前の事。 「偶には、こういうのも悪くないだろう。」 「ああ。」 少しばかり香りの強い透明な酒を杯に注いでやれば、にこりと上機嫌に笑って、返杯を促される。 「紅緋衣というはなは…わざわざ交配で作られた、自然界には無かった桜だ。他のどの桜よりも厳しい北の大地に強く気高く咲く。」 数えるほどしか見ていないその優美な立ち姿が脳裏に蘇る。それまで薄紅か白しか知らなかったが、桜と言うのは色とりどりなものだとあの時初めて知った。 「ヒトと言うのは…本当は、紅に恋い焦がれているのかもしれないな。」 禁忌の色と言われる反面、破邪の色、魔除けの色とも呼ばれる、深い紅。最も禁忌を疎んじる寺院内でも高僧の一部が纏う。遠い遠い、自分達のいる所とは地続きだとは思えないほど遠い、西の果ての国では黄色と並んで高貴な色として、聖なる色として纏える者を限定していると聞いた事もある。 返杯した後、桜の花弁が舞い散る様に向けられ続けていた、真紅の瞳が、途切れた言葉の先を促すようにただただじっと見詰めて来るのに、暁色の瞳が微笑み返す。 「お前は、俺が手に入れたい、地上に唯一枝の桜だ。」 いっそ手折って。もしも枯れる事がないなら。目に届く範囲にいつでも活けておきたいほどに。 「そんなキレイなもんじゃないだろうよ…。」 くすり、と小さく漏れる声に言葉ほどの重みはない。その笑みは言葉を受け止めていると雄弁に語り。 「葉桜ってさ。覇桜とも言われるんだぜ?覇王と引っ掛けてさ。」 知ってた?と悪戯な光を宿す緋色が揺れる。無言で自分の知らない事象に対する説明を求める視線を向ければ、笑みは益々深くなり。 「俺がお前の花なら。お前は俺の葉桜だよ。」 とうめいで、とても、とうめいで。言葉に詰まる。 葉桜なんかと同じにされちゃ堪らないだろうけれど。その強さと瑞々しさ。命の光と包み込む優しさ。その全て。秋口の紅や黄金さえもがその立ち姿に似合うと思うから。上手く伝える自信が無いから言葉には出来ないけれど。 花は先に散り、葉の姿を見る事なく終わる。葉は花の後を追い、その美しい白と時が重なる事はない。けれども、それでも同じ樹が育むもので。 一陣の風が桜の雲の上を駆け抜ける。一気に舞い上がる溶ける事のない雪。薄紅、白亜。 舞った花弁は巻き上げた風から解放されると、焦がれる者の腕に飛び込むようにゆるりと地上に落ちて来る。それを手にした杯で受け止めて、ふと柔らかな笑みを浮かべる姿に、ほんの少しだけ、ちくりとしたムネの痛みを覚えて微笑んだ緋色のヒトを抱き締める。 「今度は紅緋衣を見に行くとしよう。」 「ああ…そうだな。」 |